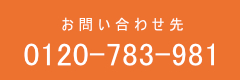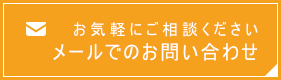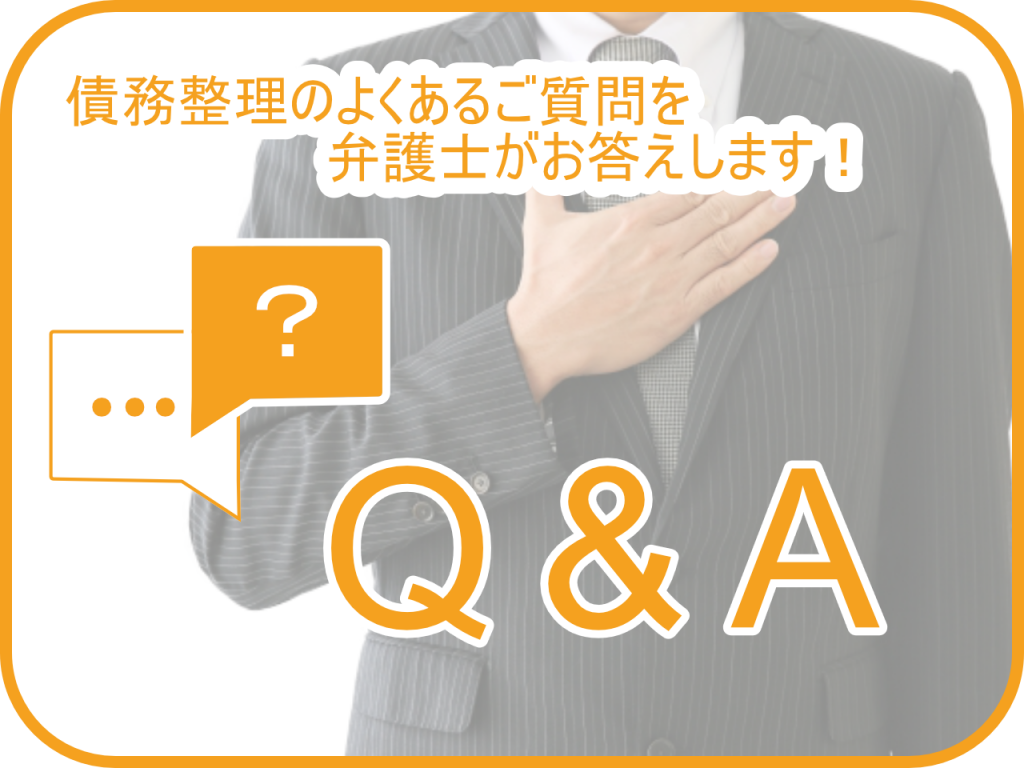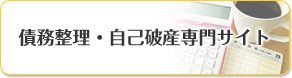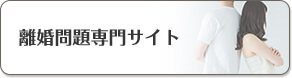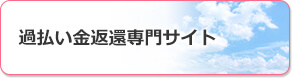いつも当サイトをご覧頂きありがとうございます。大変申し訳ないのですが、あなたがアクセスしようとしたページは削除されたかURLが変更されています。お手数をおかけしますが、以下の方法からもう一度目的のページをお探し下さい。
1.検索して見つける
検索ボックスにお探しのコンテンツに該当するキーワードを入力して下さい。それに近しいページのリストが表示されます。
2.人気の記事から見つける
- 債務整理のメリット・デメリットとは?弁護士を選ぶ際のポイントを解説
- ブラックリスト状態になるとどうなる?
- 自己破産後の生活について
- 過払い金返還請求を家族に内緒で進めるには
- 過払い金返還請求をしたくても、弁護士費用を支払えるかどうか心配なのですが?
- 債務整理を相談すべきタイミングはいつ?
- 過払い金の推定計算とは
- 過払い金返還請求をすると信用情報に問題が生じるのか
- 過払い金の返還を受けるためには
- 任意整理をした場合、何年以内に借金を返済することになるのでしょうか?
- 過払い金請求の時効について
- 過払い金とは
- 完済した借金でも過払い金請求ができるのか
- Q.債権者への返済が少しでも遅れたことがあると、過払い金返還請求はできなくなりますか?
- クレジットカードによる取引でも過払い金返還請求ができるのか
- 裁判をせずに過払い金の返還を求められるのか
- 過払い金返還請求を依頼するための必要書類
- 退職により収入が減り借金・・債務整理・自己破産はできる?
- 過払い金に利息が発生するのか
- 借入期間がどのくらいあると過払いが発生するのですか?
3.カテゴリーから見つける
それぞれのカテゴリーのトップページからもう一度目的のページをお探しになってみて下さい。
4.無効なリンクを報告する
もし当サイト内で無効なリンクを発見された場合、どのページのどのリンクが無効だったかをご報告頂けると幸いです。今後とも、使いやすいサイトになるよう精進させていただきますのでよろしくお願いいたします。